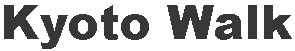
蹴上浄水場
keage
京都市東山区粟田口

05/5/11
蹴上浄水場は毎年春の黄金週間に一般公開される。場内に7000本のつつじ・さつきが植わっていて、市民がそれを楽しみに、見に訪れる。
京都市内にある4ヶ所の浄水場の中で一番古く、明治45年に竣工された。
となりにインクラインがあり、疎水が流れる。疎水と切っても切れない関係にあるのが、蹴上。
京都の水道は、疎水によって琵琶湖から流れて来る水を、取水地でその原水を取り入れ、浄水場に運ばれるのだ。
このように広大な、ゆったりした広さの浄水場。でも京都の中では一番小さいとか。
東にゆったりと東山が見える。画像のちょうど正面・真ん中には、分かりにくいけれど南禅寺だと思う、三門の屋根が。
一般公開中は、つつじは五部咲き。
ちょっと迫力がなかったけれど、それでもきれい

41KB, 40KBお天気もよく、人もたくさんいたけどみなのんびり。ああのどかです。
赤いのはキリシマツツジだろう
43KBきれいだー。と思わず接写。
写真を撮っている人がほかにも沢山いた
場内には、なぜか与謝野晶子の歌碑が。
41KB丸っこいのが可愛いんだよね。
浄水場になぜつつじがあるのかは謎
浄水場の施設、第一高区配水地とかや。いきなりレンガ作りの私好みの建物。そういえば、「九条山浄水場ポンプ室」というのは、何と宮廷建築家、片山東熊がデザインしたおしゃれな洋風建築だ。もしかして、これも??
いやいや、これはきっと建築家小原益知だろう(「京都モダン建築の発見」)。
京の水道水 疎水物語入り口で、水道水を無料で配っていて、水道のおいしさをアピール。その気になればいくつでも持って帰れるけれど、重いのでひとつで精一杯。
いやあ、名前がしゃれてますね(ほんとか)
これは、災害用備蓄飲料水で、家に持って帰って、地震のときに備えておくのだ 5年間有効
製造者はなぜか兵庫県の会社
スタンプラリーで貰える携帯ストラップ。
澄都くんという、ホタルのキャラクターだ(とほほ…)浄水場内で、スタンプラリーをやっていた。3箇所のスタンプを集めると、「京都市上下水道局マスコットキャラクター」の、ほたるくんの携帯ストラップを貰えるので、頑張ってラリーをしてみた。
といっても、場内は広く、勾配もあるので(丘を上るような感じだ)、ゼイゼイ言いながら、やっとこさもらったのだ。スタンプは、本館展示場、最高区配水地、与謝野晶子歌碑でもらえた。
なお、イメージキャラクターのホタルは、ホタルが飲むほどきれいでおいしい水、という意味合いを持たせてあるのだろう。確かに疎水にはホタルが来るのだが。
オスとメスがいて、澄都(すみと)くんとひかりちゃんという名前までついている(何だか…)。
ストラップは澄都くんオンリーだった。まつげがついていて、リボンをしているひかりちゃんが欲しかった私は少しがっかり(…)。でもこれは非売品で超レアものかもしれない!(…)そのほかに、水道局オリジナルうちわを全プレでもらえた(桜の季節のインクライン写真付き)。
この項、ついて来れない人もいるかと思いますが、ついて来て下さい。
浄水場の北隣りには由緒あるウェスティン都ホテルがあり、その北にこの建物がある。
これは蹴上発電所とのこと
やはりレンガ作りの重厚な建物で私の好みだ。
画像はよくなくてクスンです。
船を乗せた台車。浄水場の、通りを挟んだ東にはインクラインがあり、保存されています。
今は市民の散歩道で、けっこうさびれているけれど、このようにお船がディスプレイされていたりする。決してほったからしにしてあるのではない。
インクラインについては、いつかちゃんと特集をしたいものだ(そればっかり…)。
インクライン跡は歩けるようになっている。
鉄道のレールの幅よりもかなり広い、船を行き来させたレール。桜の季節に写したものだ
さて最後に蹴上(けあげ)という変わった地名についてひとこと。これは、例によって歴史的な謂れがある。
しかも、今が旬の源義経に関係している。義経が鞍馬から出て東へ向かう途中、ある武士の一行に出会ったが、その従者が、峠の水を蹴って義経の衣を汚してしまった。怒った義経は従者を斬り捨て、武士の耳鼻を削いだという。
(「京都 地名の由来を歩く」谷川彰英より)何だか義経のイメージを損なう伝説だ。ともあれこの地で義経に水を蹴り上げたというところから「蹴上」という名前になったようだ。
浄水場の住所は粟田口となっているが、この粟田口は、「京の七口」のひとつで、京から東へ向かう出口、または入り口となっていたことから付いた地名だ。
粟田という名は、平安時代以前からここに住みついていた粟田氏から来ているとかや。義経がここから東へ向かったという説は、その意味では正しそうだ。
【近所】南禅寺 無鄰庵 京都市動物園
【蹴上浄水場への行き方】
地下鉄京都駅〜烏丸御池〜東西線〜蹴上駅
京阪バス 蹴上駅
市バス 神宮道
参考「京都 地名の由来を歩く」谷川彰英 KKベストセラーズ
「京都モダン建築の発見」 淡交社
京都市上下水道局パンフレット