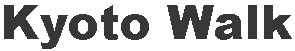
祇園祭2005
アップしそびれていた画像を、この時期に上げてしまいます。
13/12up

今年もやって来た。祇園祭の季節。祇園祭一色で埋め尽くされた京都の町は美のエクスタシーに濡れる(意味不明)。


函谷鉾(かんこぼこ) 四条烏丸交差点すぐ


函谷鉾
函谷鉾の見送りは沢山あり、1つは重要文化財に指定されている。1718年の寄付によるという。
今年亡くなった染色作家、皆川泰蔵氏のエキゾチックな「エジプト天空図」と「モン・サン・ミッシェル」が、氏を記念して今年の巡行に使われた。

胴掛け・水引・見送り 巡行までは、当たりさわりのない懸装品
巡行当日の早朝に、とっておきのものを飾る



鶏鉾
鶏鉾は、ベルギー製の絨毯を見送りに作りかえた重要文化財のものが有名。でも、宵山までは外に出さないので、巡行の時以外はとても地味。

曳き初めで ふとひと休み
座っているお兄さんの左側においてある木片は、鉾の車輪の向きを変えるためのもの。
これで、鉾の進む方向をコントロールする

鶏鉾 室町四条下ル
32基ある山鉾では、それぞれがその山鉾のロゴ入りコスチュームを持っている。イナセだね。
そればかりか、浴衣、手に持つ扇なども、山鉾オリジナルのものだ。


月鉾 四条室町西
月鉾の屋根裏には、円山応挙の「金地彩色草花図」が描かれているという。と言うわけで、上を向いて撮ってみたが分かるでしょうか。


月鉾の曳き初め エーンー、ヤーラーヤァー
一番のみどころだ
月鉾音頭取りのお方の浴衣は、荒い織の麻製だった。そのせいで、歩いておられると、生地がスケスケでボディラインが丸見え。もう何から何まで、アレからアレまでがもろ見え(謎)。ありがとうございました(謎)。

月鉾で使う扇はお月様の模様入り。表が金地に三日月、裏は銀地。

月鉾

菊水鉾 唯一の唐破風造りの屋根を持つ
菊水鉾は昭和になって再建された鉾。多分1864年の禁門の変で焼けた。鉾頭に金の繊細な菊花を置き、謡曲「枕慈童」にちなむ。
稚児人形は菊慈童…オレンジ色の艶やかな懸装掛けとともに、色っぽさただよう鉾だ。

長刀鉾 四条烏丸東
唯一、現代でも人間の稚児が乗る。くじ取らずで、常に山鉾巡行の先頭をつとめる由緒ある鉾。

ああっ、ぶれてしまった


稚児舞いを披露するお稚児さん